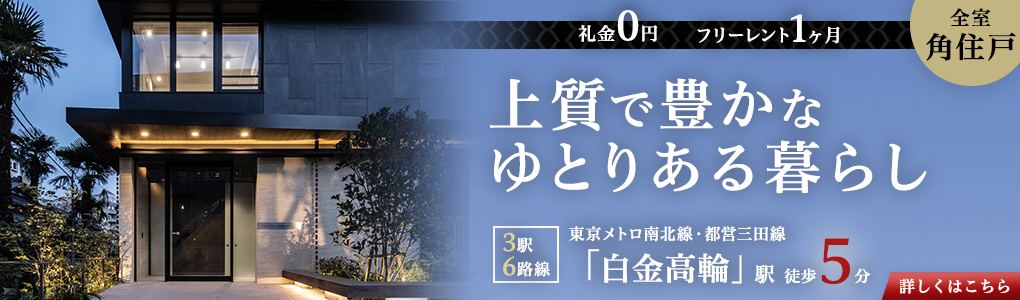厚生労働省は今月中にも、テレワークについての企業向けガイドライン(指針)の見直し案を報告。2018年2月に策定された以前までの指針では、企業は従業員の労働時間をパソコンの使用状況や客観的な記録で確認することが原則とされていました。それが今回緩和され、働き手からの自己申告を認めると明記。テレワークの現場は、どのように変化し、何が問題となる可能性があるのでしょうか。
新ガイドラインのポイント
日本経済新聞によると、新たなガイドラインの主な内容として以下の項目があげられています。
・労使で労務管理ルールをあらかじめ決定
・業務フローの電子化を推進
・テレワーク通信費など費用負担も考慮を
・深夜・早朝を含め始業や終業時間は柔軟に設定
・長時間労働対策に業務システムへのアクセス制限なども検討
・健康相談体制やコミュニケーション活性化の措置を
引用:日本経済新聞
この中でポイントとなるのが、労働時間の確認方法です。新ガイドラインが施行されると、労働時間の確認方法は、パソコンなどの使用状況を把握する方法のほか、働き手の自己申告での確認も可能となります。育児や介護などで中抜けなどをする場合も、終業時間を遅くしたり、早朝時間を活用したりするなど、個々に合わせた柔軟な働き方がしやすくなるでしょう。また休日や深夜労働の場合は、割増賃金も考慮する必要性も示されています。

新ガイドライン適用後のテレワークの問題や課題
これまで子育てのために中抜けをする働き手は、企業によっては肩身の狭い思いをしてきたでしょう。国が指針を出すことで、堂々と中抜けができ、その分を違う時間帯で補えるのであれば働き手としても制度を活用しやすいはずです。
しかし自己申告では、オンオフの区別がつきにくく、長時間労働になってしまう可能性もあります。業務システムへのアクセス制限をすることで、長時間労働は制限できますが、業務システム外で作業する働き手も出てくる可能性も否定できません。これまで以上に、こまめな進捗状況の実施や働き手とのコミュニケーションを図ることが重要となります。

長時間労働対策
テレワークでの勤務は、長時間労働に対する対策が必要です。厚生労働省では先程記した業務システムへのアクセス制限のほか、以下の点も有効としています。
1.時間外のメール送付を抑制
役員などから、部下へ休日や深夜における業務指示のメール送付を自粛することで、働き手の長時間労働を抑制できます。指示はできるだけ業務時間内で作業が終わることを逆算した時間帯に送ることが大切です。
2.時間外、休日、深夜労働の原則禁止
就業規則などに、時間外、休日、深夜労働の原則禁止、もしくは企業側の許可制とするなどを明記しておくことも重要でしょう。
3.注意喚起の徹底
労務管理システムを使用して、長時間労働者に対して自動で警告を出すなどの方法が推奨されています。
しかし労務管理システムを使用していない企業や、システム外で長時間労働をしてしまう場合は、働き手の勤務状況は把握できなくなります。できる限り、システムの導入をし、時間内で勤務が終わるように互いにコミュニケーションを取っていくことが大切です。

労働時間の自己申告が認められた場合でも、「長時間労働を厭わない」という企業体質が変わらなければ、新たなガイドラインは意味を持たなくなってしまいます。旧体制からの脱却が最重要課題となる企業もでてくるでしょう。また、働き方の変化を敏感に察知した優秀な人材は、そういった体質の古い企業で働くことは避けることが考えられますので、抜本的な社内改革が求められるはずです。

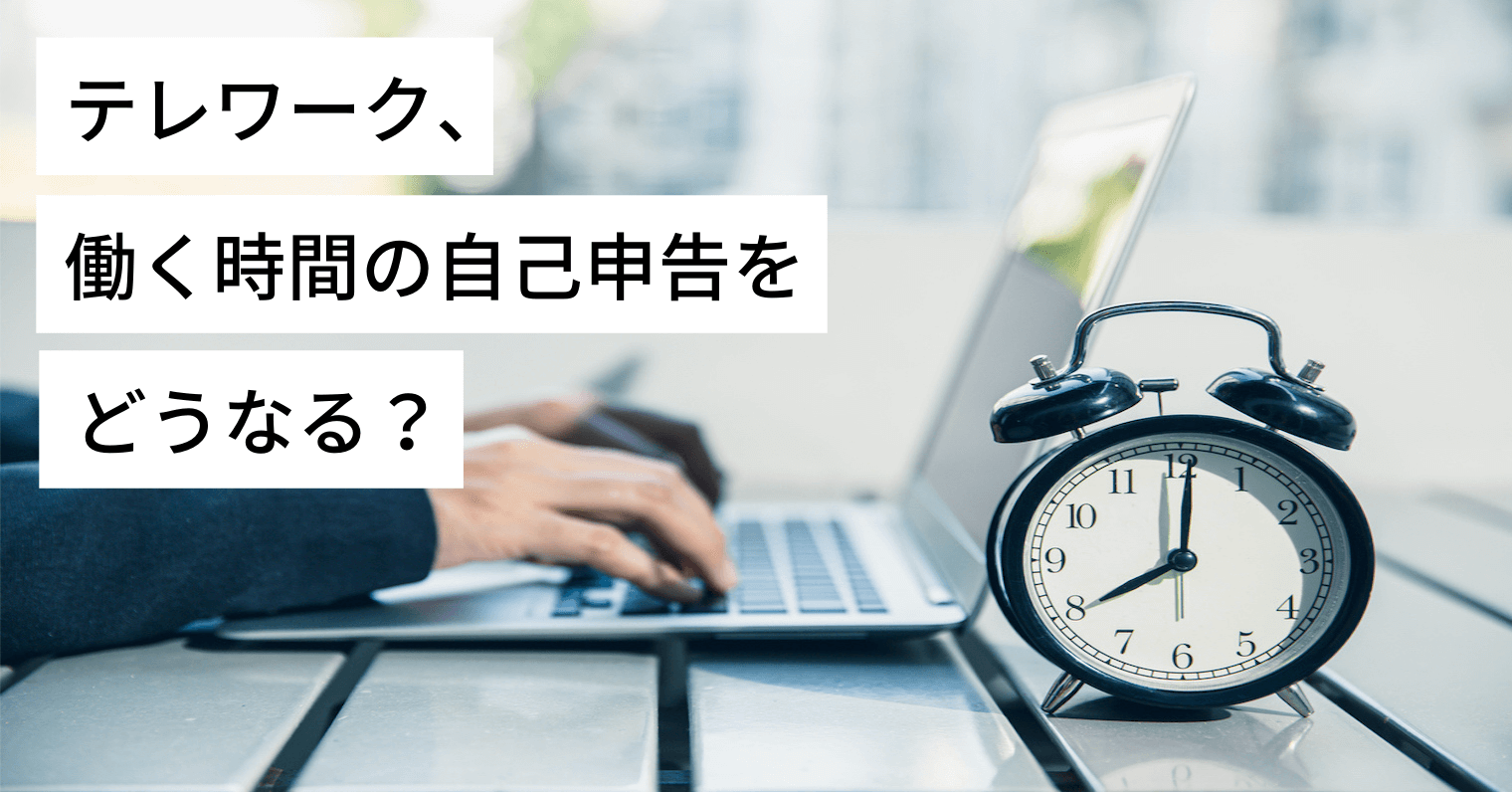
 Share
Share