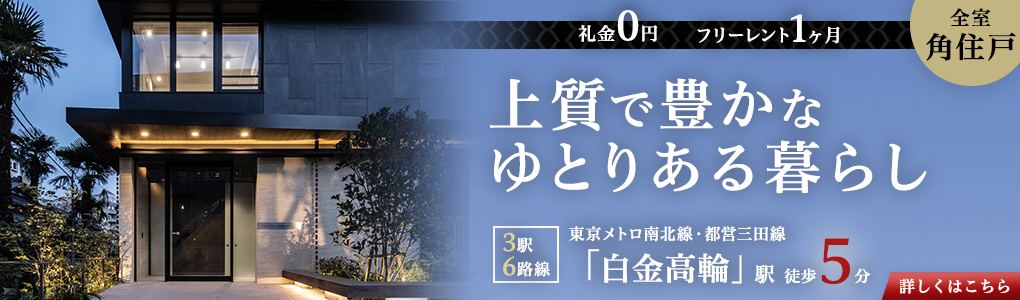こんにちは!編集部員のアッキーです!
みなさんは、仕事でチャットのやり取りをされてたりしますか?
これまではメールでの連絡が多かったかと思いますが、いよいよビジネスチャットというカテゴリーも普及し、ビジネスのスピード感がガラリと変わった印象を受けます。
この記事では、冒頭に触れたようにビジネスでチャットを使ってコミュニケーションを取ることによっての効果について書いていきます。
こう使うともっと便利!という活用法もあげていますのでぜひ読んでみてください。
1.ビジネスチャットが普及している理由とは

ソフトバンクの孫社長の経営判断の速さというのは凄まじいそうですね。
成功している社長、企業、業界から見て、このスピード感が経営そのものに直結していると言えるのではないでしょうか。
そんな中、業務で行うコミュニケーションをこれまでのようにメール、電話、もしかするとFAX(!?)でのやり取りが通例になっていては、どう頑張っても「速さ」を求めるには物足りないツールなのではないでしょうか。
もちろん、時と場合によってこれらを使い分けることが一番大事なのですが、メインとなるコミュニケーションをビジネスチャットに置き換えることで、やり取りや情報共有、そして意思決定が格段に速くなることは間違いありません。
2.メールとビジネスチャットは意思決定のスピードが違ってくる

では、なぜそのスピード感を生み出すことが出来るのか?
メールとビジネスチャットの違いについてご説明します。
まず一つ目に、メールは基本1対1を想定したコミュニケーションツールで、CCやBCCへ複数名メンバーのアドレスを入れて送信することができますが、仕様上タイムリーなやり取りをするにはあまり向いていません。
一方で、ビジネスチャットは、グループチャットでやり取りをすることを基本に設計されています。
1対1でのやり取りも出来ますが、情報が属人化しないよう同じプロジェクトや業務の話題は関連しているメンバーが含まれたグループチャットで行うことが推奨されています。相互的なコミュニケーションを取ることが出来るので、一つひとつの意思決定が非常に速くなります。
二つ目に、やり取りを整理しやすく探しやすいかどうかという点です。
メールであれば全てのメールは受信ボックスに届くので、細かなフォルダ分けが必要になりますが、ビジネスチャットでは話題や相手ごとに表示されているため整理しやすく、また検索性が優れているので過去のやり取りとその前後関係を効率よく確認することができます。
三つ目に、簡潔なやり取りができるかどうかです。
メールのお決まりの冒頭文面がありますよね。
◯◯様
いつも大変お世話になっております。
◯◯の◯◯でございます。
というご挨拶文面です。加えて署名を必ず最後に入れますよね。
ビジネスチャットでは「お疲れ様です」の一言も省略して本題から、しかも短文で簡潔に発信するのです。このおかげで要点が伝わりやすく、コミュニケーションの活性化にもつながるのです。
3.個人のSNSに付随するチャットで大丈夫?

個人で利用するSNSツールで仕事のやり取りを頻繁に行うことはあまりオススメしません。
セキュリティの観点と、人為的なミスが起こりやすいという点です。
その他にも、ちょっとしたやり取りでは気軽でとても便利ですが、データの受け渡しをしたり、エビデンスとしてログを残しておきたい場合には機能的に不足していると言わざるを得ません。
便利な活用方法として、ぜひチェックしておきたい機能をご紹介します。
まだビジネスチャットを導入されていない場合は参考にしてみてください!
<ビジネスチャット活用法からみる推奨機能>
◆メンション機能・返信機能
グループチャットで、誰宛のメッセージなのかがわかるように発信することで最適な相手から返信がある状況をつくることができます。
また、返信機能では、誰からの何に対する返信なのかが明確になることで的確なやり取りが可能です。
◆引用機能
返信よりも確実に文章を捉えて、それに対するコメントをすることができます。
また、部分引用が可能なツールであれば、より精度が高いやり取りが可能です。
◆未読に戻す機能
一度開いて既読になったメッセージを未読に戻す機能で、対応漏れがなくなります。
後で返信しようと思っていても、記憶に残しておくだけでは抜け漏れの原因となるため、未読にさえしておけば気づくことができやすくなります。
◆タスク機能
メッセージはフィードに流れてとどめておくことができません。
タスク(ToDo)機能を活用して、やるべきことを「完了」するまでToDoとして残しておくことができれば、グループチャット内でタスクを確認・実行・完了まで管理することができます。
いかがでしたでしょうか。
まだまだビジネスチャットを活用する方法はたくさんあります。
どのような業種業態、またプロジェクトで活用するかによって他のアプリとの連携などに拡張していくことも可能です。
目的に応じて使いこなしていきましょう!

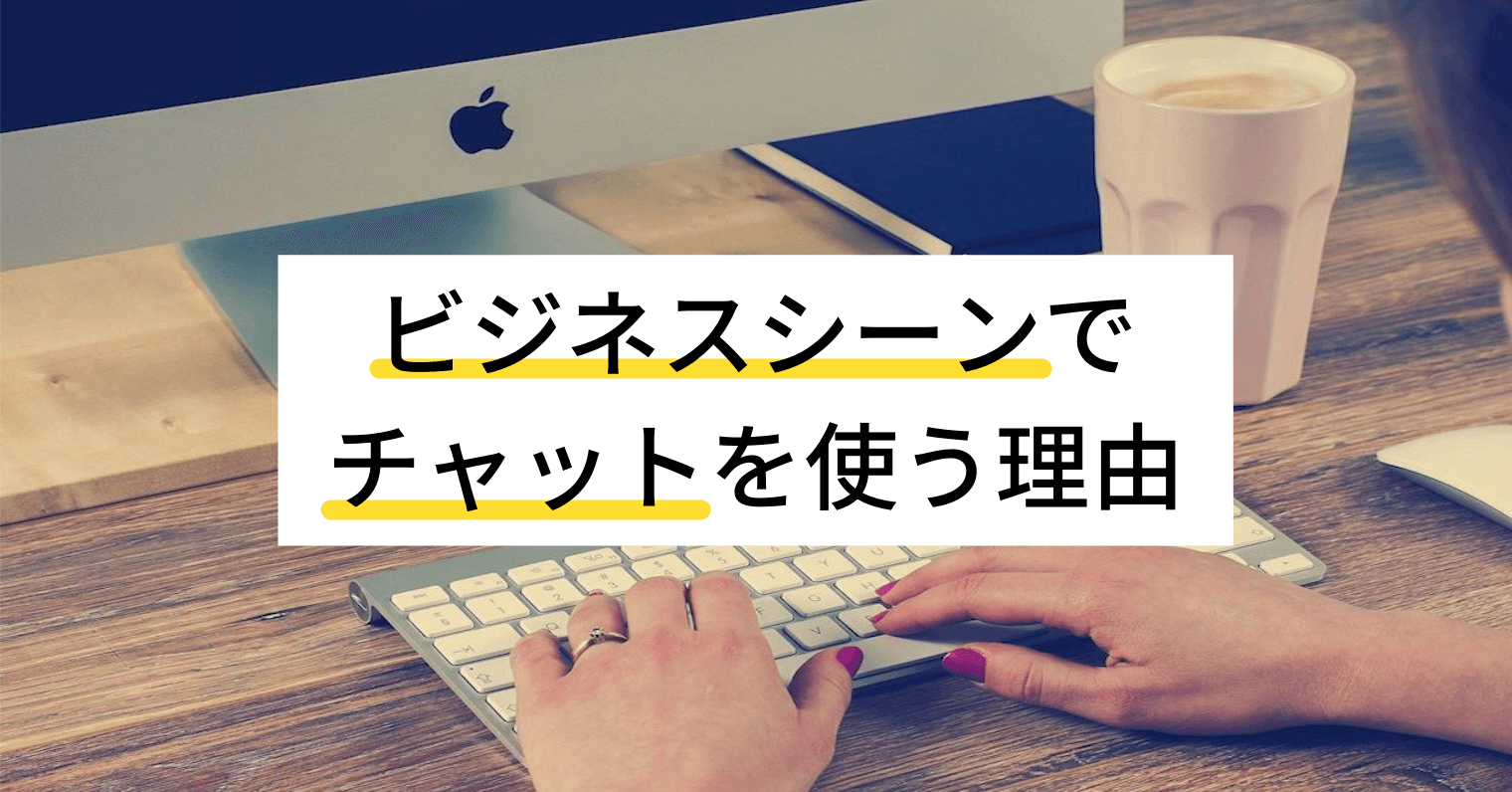
 Share
Share